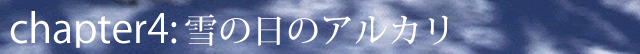|
|
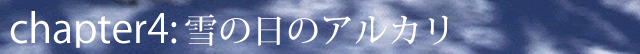 |
 |

寒い夜だった。わたしはその日えらく分厚いロシアの小説を読んでいて、気がついたときにはもう深夜だった。部屋のカーテンさえ閉め忘れていた。ときどき、そういう種類の本に出会うことがある。本に集中しすぎて現実のことを何もかも忘れてしまうのだ。
閲覧室は異様な寒さだった。やっとそのことに気がついた。わたしは季節をまちがえて卵から孵ってしまった雛鳥だった。鳥肌だってちゃんと立っていた。でももう殻の中に戻ることはできそうになかった。だからわたしは窓のところまで歩いていった。それでわかったのだった、どうしてこんなに寒いのかが。この冬はじめての雪だった。
いったん気がついてしまうと、部屋の寒さは耐え難いものになった。困ったことにストーブには一滴も蜂蜜糖油が入っていなかった。わたしたちは蜂蜜糖をある特別な方法で発酵させて、よく燃える蜂蜜糖油を精製する。いつもなら、もうしっかり用意を整えている時期だった。ここの冬はとても寒いから、ストーブに火を入れられないのはまさに致命的なのだった。これでは夜明けまでにはすっかり凍え死んでしまう。わたしは図書館の裏の離れにある倉庫までいって、蜂蜜糖油を運んでこなければならない。凍死する前にしたことがロシアの小説を読むことだったなんて、誰が聞いたって凍えそうではないか。わたしはわたしの墓の前に立つ見知らぬ誰かを凍えさせたくなんてなかった。
「ロシア人の書いたものに没頭し
ロシアのように寒い部屋で凍死」
仕方がないな。わたしはお気に入りの黒いダッフルコートを羽織って外に出た。
雪はかなり積もっていた。まだしばらくは止みそうになかった。とても寒い。それでもわたしはうっすらと明るい灰色の空を見上げて、降ってくる雪が口の中に入るようにした。子どものころ、あなたもきっとそうしたことがあるだろう。でもここの雪は、ほかの雪とはちょっと違う。そう、ここの雪はかすかに蜂蜜の味がするのだ。わたしは心ゆくまで思うぞんぶん、降ってくる雪を味わった。といっても、ちょっとずつしか口の中には入ってこない。とてもじれったいのだ。
やがて鼻がもぎとれてしまいそうになった。もうそれ以上は上を向いていられなかった。限界だった。わたしはやるべきことをやらなければならない。鼻ならいつだってもぎとることが可能なのだ。もちろん、もしそうしたければの話だ。いましなければならないのは、ストーブに火を入れること。そのために倉庫から蜂蜜糖油を運んでくること。わたしは今度は下を向いて倉庫まで歩いた。顔がひりひりして、もうちょっとでも雪が触れるのが嫌だったのだ。どうやらわたしは少し調子に乗りすぎたみたいだった。寒さで顔がはちきれんばかりだった。
わたしがそれを見つけたのは倉庫の手前だった。すでにそれは新しく降り積もった雪で、薄く、いまにも見えなくなってしまいそうだった。下を向いて歩いていたおかげで、わたしはそれを発見することができたのだ。でも、あとちょっとでも遅かったら、わたしはそれに気づかなかったに違いない。雪は、そこに辛うじて刻まれた生命のしるしをかき消そうとするかのように容赦なく降っていた。すべてを無垢のもとへ返そうとする不穏な爆撃のように、大地の上にまっ白な正義を叩きつけていた。でもそんなことを黙って見過ごすわけにはいかない。そのような正義ならいらない。わたしはいそいでその小さな足跡をたどった。予想通り、それは倉庫の裏側へと続いていた。間に合えばいいのだけれど、とわたしは思った。前にもいちどこういうことがあったのだ。
わたしはその日、明け方までウィスキーをがぶ飲みして気分が悪くなり、自分の赤ん坊が生まれたことを知らされた父親のように急いで外へ出て、気分が悪くなる元を吐き出したのだった。そのときはトイレよりも外の方が近いような気がしたのだ。わたしの吐き気はどうにか間に合った。でもその猫は駄目だった。かわいそうに、もう冷たくなっていた。その身体がどんなに冷たかったのか、ここに書くことはできない。そんなことを、ことばにすることはできない。だから、今度は間に合えばいいのだけれど、とわたしは思ったのだ。
倉庫の裏側のひさしの下に仔猫が丸くなっていた。まだ大丈夫みたいだった。全身が灰色の、まだほんとうに幼い猫だ。小さな身体をさらに小さく丸めたままで、わたしが近づいても仔猫はまったく逃げる様子を見せなかった。おそらく、寒さでもう動けなくなっているのに違いない。わたしは仔猫を抱き上げた。とても軽い。わたしはしばらくのあいだ仔猫をわたしの体温であたためてやった。仔猫はぶるぶると震えていた。それがあたたかいものでありさえすれば何でもいいとでもいうように、わたしの腕にしがみついていた。わたしはコートのポケットに仔猫を入れて、いそいで倉庫の中に入った。仔猫はポケットの中で、まるで空っぽみたいに軽かった。そこにいるという感じがしないのだ。身体の中から何か大切なものが抜け出てしまったんじゃないかと心配になるほどだった。
心をこめて、とことばでいうことはたやすい。だが実際にそうすることは、ひどく難しいものだ。でもそのときのわたしは、心をこめて仔猫があたたまるよう努めたと思う。これでもしこの仔猫が元気にならなかったら、わたしはもう二度とロシアの小説なんか読むまい、と決心したほどだ。前の猫のことがあってから、ウィスキーを飲むのをやめたように。
わたしはてきぱきと動いた。そのおかげで身体があたたまり、もうストーブなんていらないくらいだった。わたしは仔猫を毛布でくるみ、わたしが読んでいたロシアの小説の上に寝かせた。ストーブの火がほどよく当たるように。そのロシアの小説にも、何か手伝わせるべきだとわたしは思ったのだ。もしわたしがもうちょっと早く寒さに気づき、蜂蜜糖油をとりにいっていれば、もっと早く仔猫に気づくことができたかもしれない。その小説のおもしろさによって、救出が遅れたことは確かなのだ。なら、せめてもの罪滅ぼしをするべきなのだ、そのロシアの小説も。ときどきロシア人は、あまりにも長く、あまりにもおもしろい小説を書きすぎる。
わたしは閲覧室のソファの上で眠ってしまっていた。気がついたとき、猫はわたしのひざの上で眠っていた。いったいどうやって上ったのだろう、とわたしは思った。猫がわたしのひざの高さまで飛び上がることができるようにはとても思えなかったのだ。でも確かに猫はわたしのひざの上にいた。もう震えてはいなかった。大事な人からの贈り物のように猫はあたたかさを取り戻していた。わたしは仔猫の首筋をなでながら、仔猫につける名前を考えてみた。わたしはもうその猫を飼うことに決めていたのだ。「アルカリ」なんてどうだろう、とわたしは思った。それは、確かアラビア語で「灰」を意味したはずだ。雪の日のアルカリ。
「アルカリ」とわたしは呼んでみた。アルカリはまだすやすや眠っていた。砂漠のように茫漠とした眠りの中をどこまでも突き進んでいた。
そうだ、〈蜂蜜公園〉には〈蜂蜜公園〉よりもちょっとだけ広い砂漠があるのだ。いったいどういうことなのか、あなたは不思議に思うかもしれない。わたしだってそうだった。ある広がりの中にそれよりも広い広がりが存在する、というのはどう考えても奇妙なことではないか。でもこの世界ではときとしてそういうことがあり得る。常識に囚われていてはいけない、ということの見本のようなものだ。〈蜂蜜公園〉には〈蜂蜜公園〉よりもちょっとだけ広い砂漠がある。
その砂漠ではあらゆることばが砂の中に埋もれて、どこにも届くことがないのだといわれている。いつでも砂混じりの強い風が吹きつけていて、そこではわたしたちのことばは、すぐそばにいる人の耳にも届かない。というよりも砂嵐のノイズのせいで、ほとんど耳はさえぎられてしまうのだ。だから発した声が自分自身の耳に届くかどうかだって怪しいものだ。そばに誰かがいるのかどうかさえ、すぐにわからなくなってしまう。細かい砂の粒はどこにでも入りこんでくる。だから目を開けることができないのだ。そもそも砂の粒がぶあつい雲のように空をおおっていて、太陽の光が届かない。太陽が、果たして、どこかにあるのかどうかさえもわからない。鼻の粘膜にはびっしり砂の粒がはりついてしまうので、口のまわりいっぱいに蜂蜜がくっついていても何の匂いも感じられない。服の上からでも入りこんでくる砂のせいで、皮膚という皮膚がくまなくコーティングされて、右手が左手に触れていることさえもわからなくなる。声を出そうとした瞬間に、砂の粒が目いっぱい口の中に入ってくる。それはこの世のものとは思えないほどに苦く、もう二度と口を開けようなんて思わないほどらしいのだ。運良く声を発することができたとしても、あっというまに、いや、あっというまもなく、声のまわりを砂の粒が取り囲んで、その重みで声は墜落して砂漠の一部になってしまう、といわれている。そして、そのすべての砂の粒は、そのように墜落した声の残骸なのだ。声は重い砂の塊となり、金属のように硬くなる。やがて、途方もなく長い時間をかけて砕け、細かい砂の粒になり、砂漠に吹きつける砂嵐になるのだ、といわれている。
わたしたちのいい方では、「〈蜂蜜公園〉には〈蜂蜜公園〉よりもちょっとだけ広い砂漠がある」といういい方になる。でも、ほんとうはこういうことかもしれない。ここにはもともと砂漠だけがあった。そしてその一部分に〈蜂蜜公園〉を築き上げた、ということなのかもしれない。スケートリンクのまん中に、ホットカーペットを敷いたみたいに。わたしたちはいまでは、とてもではないがそんなことは信じられない。〈蜂蜜公園〉はその土台の上をすみずみまでおおっているのだ、と思いがちなのだ。でも、〈蜂蜜公園〉には〈蜂蜜公園〉よりもちょっとだけ広い砂漠があるといわれている、そのことだけは確かで、わたしたちはそれを忘れてはいけない。それがいったいどういうことを意味するのかわからなくても、そのことについて忘れてしまってはいけないとわたしは思う。それがことばの届かない場所から届く、ただひとつのことばなのかもしれないのだから。
わたしはそのようなことばの届かない砂漠のような眠りを妨げないように、そっとアルカリを抱き上げた。わたしの座っていたソファの上に寝かせようと思ったのだ。わたしのひざの上はあんまり寝心地がよくなさそうだったから。でもアルカリは起きてしまった。猫はそういうとき、だいたいは起きてしまう。まだ慣れない場所だし、眠りも浅かったことだろうから。
「はじめまして」とわたしはいった。「今日からきみはアルカリだよ。どうだい?」
もちろんアルカリは何も答えなかった。まだ砂漠から帰ってきたばかりなのだ。それに「どうだい?」なんていわれても困ってしまうに違いないのだった。猫は自分で名前を選ぶことができない。そういうなら、わたしたちだって自分の名前を選ぶことはできないんだった。忘れていたけれど。
|
|